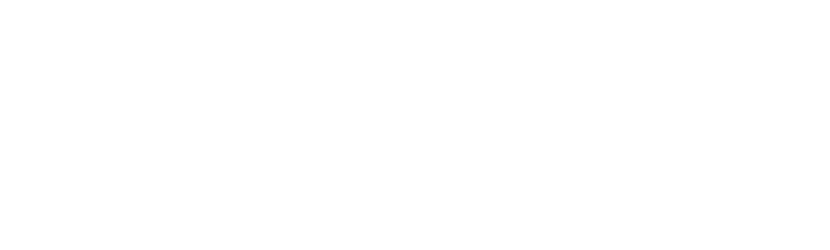【やきもんロワイヤル副読編 ~やきものこぼれ話~】 第2回「本格的なやきものの登場と、地方へ広がる窯(かま)」
20/06/22
月刊「モーニング・ツー」
(毎月22日頃発売)にて、竹谷州史氏が描くやきもの擬人化コメディ『やきもんロワイヤル』。
この作品の監修を務める日本美術ライターの橋本麻里さんに、やきもの知識満載のコラムをお願いしました。
毎月これを読めば『やきもんロワイヤル』がさらに楽しめるようになること請け合い!
(第1回はこちら )
平安時代に入ると、翡翠のような艶やかな緑色の釉薬をかけたやきものは、平安京近辺のほか、東海地方の猿投窯(愛知県尾張地方)が生産の中心となった。なぜなら、猿投窯は古墳時代から高温での焼成を必要とする須恵器を作成できる技術力、さらにそれらを全国へ流通させる生産力を持った、国内トップレベルの窯だったからだ。
奈良時代に中国の青磁を真似た、低温での焼成+緑釉の陶器が登場した際、既に高温での焼成技術を持っていた猿投窯は、9世紀に高温での焼成と釉薬の技術を組み合わせ、灰白色の生地を轆轤で挽いてシャープに造形し、その表面を淡緑色~黄緑色の釉薬がたっぷりと覆う、「灰釉陶器」を生み出した。中世以降、近世、近代、現代まで連綿と続く日本のやきものの出発点こそ、この高温での焼成+施釉のやきもの、「灰釉陶器」なのだ。
※灰釉……植物の灰を主成分とした釉。もともとは焼成中に、燃料の薪の灰が器に降りかかり、素地に含まれる成分と化合して、偶然に釉となったもの(自然釉)。自然釉の場合は、表面に点々と散ったり、一部を覆い、流れるような形で現れる。
 灰釉有蓋壺(かいゆうゆうがいこ) 平安時代・10世紀、高28.5╳口径12.1╳底径17.4cm、東京国立博物館蔵
灰釉有蓋壺(かいゆうゆうがいこ) 平安時代・10世紀、高28.5╳口径12.1╳底径17.4cm、東京国立博物館蔵
10世紀以降は灰釉陶器の量産化が実現、猿投窯は急速に東海地方一帯へと、系列の窯場を増やしていった。その結果、「灰釉陶器」は京の寺院や貴族だけでなく、北海道以外の東日本全体へ運ばれ、日常の容器として使われるようになる。ところが行き過ぎた大量生産の結果、11世紀になると猿投でも隣の美濃でも、釉薬をかけることをやめてしまい、多様だった器の形は、単純な碗や皿に集約されていった。
12世紀はじめ、これら猿投系列の窯群の中から、新しい動きが起こる。貴族による律令国家体制は終焉に向かい、武士たちが政治の実権を握っていく——巨大な社会変動と軌を一にする変化が、やきものの領域でも起こっていた。
その先駆けとなったのが愛知県知多半島の「常滑焼」と渥美半島の「渥美焼」である。両者を代表するのが、貯蔵に用いる大型・無釉(自然釉)の甕や壺。使うのは、少しずつ経済力を身につけてきた庶民たちだ。轆轤を使わない粘土紐の巻き上げ成形で、技術的にはむしろ後退している。だがそれまで中国、朝鮮半島のやきものをモデルとして追いかけてきた日本人が手本なしにつくり始めた、「日本らしいやきもの」ということもできるだろう。
常滑焼は赤褐色。渥美焼は淡い灰色を呈し、さらに渥美焼は表面にヘラを使った線彫りで文様を描くものが多い。日本でつくられた陶磁器の国宝作品を代表する「秋草文壺」(慶應義塾大学所蔵)は、同様に秋草の揺れる日本の原風景を写したものだが、これは12世紀に渥美で焼かれたものだ。
 常滑・自然釉三筋壺(しぜんゆうさんきんこ) 平安時代・12世紀、高23.7╳口径11.7╳底径7.6cm、東京国立博物館蔵
常滑・自然釉三筋壺(しぜんゆうさんきんこ) 平安時代・12世紀、高23.7╳口径11.7╳底径7.6cm、東京国立博物館蔵
 渥美・自然釉蓮弁文大壺(しぜんゆうれんべんもんたいこ) 平安時代・12世紀、東京国立博物館蔵
渥美・自然釉蓮弁文大壺(しぜんゆうれんべんもんたいこ) 平安時代・12世紀、東京国立博物館蔵
地方での窯の勃興は以後ますます活発になっていく。12世紀末~13世紀初めには、常滑焼の影響を受けた「越前焼(福井県丹生郡)」が生まれ、13世紀中頃になるとやはり常滑焼の影響下で、「丹波焼(兵庫県多紀郡)」が開かれた。他にも大小さまざまな常滑系列の窯が地方につくられていくが、中でも現在まで存続しているのが、本家の「常滑焼」、そして「信楽焼」、「丹波焼」、「越前焼」である。いずれも無釉の焼き締め陶で、赤褐色に焼き締まった肌に、青、黄、白みを帯びた自然釉が雪崩れかかった、作為のない、力強い姿が特徴で、それぞれを見分けることは専門家でも難しい。
 越前・自然釉大壺(しぜんゆうたいこ) 室町時代・15世紀、高46.8╳口径17.9cm、東京国立博物館蔵
越前・自然釉大壺(しぜんゆうたいこ) 室町時代・15世紀、高46.8╳口径17.9cm、東京国立博物館蔵
 丹波・自然釉大壺(しぜんゆうたいこ) 室町時代・15~16世紀、高45.0╳口径16.1╳底径14.9cm、東京国立博物館
丹波・自然釉大壺(しぜんゆうたいこ) 室町時代・15~16世紀、高45.0╳口径16.1╳底径14.9cm、東京国立博物館
 信楽・自然釉刻文大壺(しぜんゆうこくもんたいこ)室町時代・15世紀、高42.9╳口径15.2cm、東京国立博物館蔵
信楽・自然釉刻文大壺(しぜんゆうこくもんたいこ)室町時代・15世紀、高42.9╳口径15.2cm、東京国立博物館蔵
一方、12世紀末に釉薬をかけたやきものを復活させた瀬戸窯は、他の窯とは異なり、中国陶磁を手本とする高級な施釉陶器を生産する、当時唯一の窯となった。瀬戸窯は猿投窯の系譜を引く灰釉を用いたが、技術を改良した結果、朽葉色と形容される淡い黄褐色の釉薬、さらに鎌倉時代後期頃には、灰釉に酸化鉄を混ぜ、濃い褐色を呈する鉄釉が加わる。
 古瀬戸・褐釉巴文四耳壺(かつゆうともえもんしじこ)南北朝時代・14世紀、東京国立博物館蔵
古瀬戸・褐釉巴文四耳壺(かつゆうともえもんしじこ)南北朝時代・14世紀、東京国立博物館蔵
 備前・経筒、平安時代・12世紀、東京国立博物館蔵
備前・経筒、平安時代・12世紀、東京国立博物館蔵
以後、室町時代中期までの約300年にわたって、瀬戸窯では主に武士たちを顧客として、中国陶磁の櫛描き文様を写し、その上からこの2種の釉をかけた壺や瓶子、また仏具、香炉、茶入、天目茶碗など、多彩な器が焼かれた。
もう一ヵ所、「備前焼(岡山県備前市)」は釉薬をかけずに素地の味わいを生かすタイプのやきものだが、古墳時代来の須恵器の窯を出自とするため、これも常滑系とは一線を画する。鎌倉時代までは須恵器同様に灰青色のやきもので、「備前焼」の特徴として広く知られる赤褐色の肌が生まれるのは、それ以後のことだ。
こうして平安末~鎌倉時代に興り、中世のやきものの中心となって活動、現在まで存続している「常滑焼」、「信楽焼」、「丹波焼」、「越前焼」、「瀬戸焼」、「備前焼」を、「六古窯」と呼んでいる。またそのうちには数えられないものの、「珠洲焼」や「渥美焼」などもあり、中世の窯は多岐に栄えていた。

橋本麻里(はしもと・まり)
日本美術を主な領域とするライター、エディター。公益財団法人永青文庫副館長。金沢工業大学客員教授。著書に『美術でたどる日本の歴史』全3巻(汐文社)、『京都で日本美術をみる[京都国立博物館]』(集英社クリエイティブ)、『変り兜 戦国のCOOL DESIGN』(新潮社)、共著に『SHUNGART』『原寸美術館 HOKUSAI100!』(共に小学館)、編著に『日本美術全集』第20巻(小学館)。ほか多数。