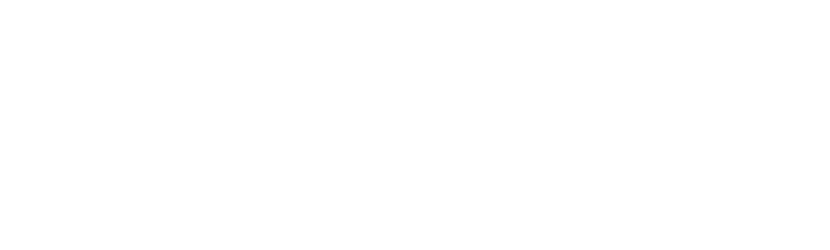【やきもんロワイヤル副読編 ~やきものこぼれ話~】 第1回「やきものは人類史を変えた!?」
20/05/22
月刊「モーニング・ツー」(毎月22日頃発売)にて、竹谷州史氏が描くやきもの擬人化コメディ『やきもんロワイヤル』。
この作品の監修を務める日本美術ライターの橋本麻里さんに、やきもの知識満載のコラムをお願いしました。
毎月これを読めば『やきもんロワイヤル』がさらに楽しめるようになること請け合い!
やきもの、というと身近にあって当たり前の、何なら100円ショップでも購入できる生活必需品、そうでなければ趣味として愛玩し、蒐集する高額な嗜好品、というイメージがあるかもしれない。だが「土を焼いてつくった器」の出現は、人類史を大きく変えた、ターニングポイントのひとつでもあった。これから5回にわたって、世界でも稀な「やきもの」大国である日本のやきものの歴史を、駆け足でご紹介していこう。
文字の発明・使用以前を先史時代と呼ぶが、その第1段階である旧石器時代の特徴は、遊動的な生活スタイル。つまり朝起きると同時に食物を求めて動き出し、狩猟、漁労、採集などの手段で食物を確保できればそれを食べ、食べ終わってしまえばまた動く。人類は世界中のあらゆる地域でこの第1段階を通過して、第2段階である新石器時代へ入っていった。縄文時代は、日本における新石器時代にあたる。そして世界でも最古級の「やきもの」が生まれた時代でもあった。日本列島で発見された最古の土器は、約1万5千年前に生まれ、以後1万年にも渡って作り続けられた。ちょうどこの頃、少人数の集団で遊動しながら生活していた人間の暮らしは、一ヵ所に腰を据えて暮らす定住型へと変化しつつあった。人間が生み出した最古の道具は石器だが、それに続く土器の発明は「人類最初の大事件」(ヴィア・ゴードン・チャイルド)に喩えられる。定住とほぼ重なる時期からつくられ始めた土器は、革袋や樹皮の編み籠など土器以前の「容器」と比べ、作るのに時間や手間がかかり、重くかさばるため、持ち運びにも向いていない。だが他方で、長期の使用や内容物の密封、液体を溜めること、火にかけることが可能になるなど、それまでの器とはまったく異なる使い方ができるようになった。
中でも煮炊きの効果は甚大だ。ものを煮ることで、灰汁や毒を抜いたり、柔らかくできるため、人々が口にできる食べ物の種類は大幅に増えた。食べるものの多様性が増せば、ある食物が不作の年でも、別の食物を食べて飢えを凌げる。縄文土器の存在は、定住とセットで、生活を豊かで安定したものに変え、人口を増やす契機ともなっていった。
こうして何世代もが同じ場所を住み継いでいくうちに、人々は風土に適応した文化を育んでいく。「方言」や「名物料理」がその土地らしさを感じさせるのと同じように、ある期間、一定の地域のまとまりの中で、火焔型や水煙型など、特徴的な形や文様が形づくられていった。遥か先の時代に登場する「◯◯焼」というあり方とは異なるものの、つくり手たちは明確に、「これが自分たちのデザイン」という意識を持って、土器をつくっていたと考えられている。
 火焰型土器 縄文時代(中期)・前3000~前2000年、高35╳口径28╳胴径20cm、伝新潟県長岡市馬高出土、東京国立博物館蔵
火焰型土器 縄文時代(中期)・前3000~前2000年、高35╳口径28╳胴径20cm、伝新潟県長岡市馬高出土、東京国立博物館蔵
その後、弥生文化——「日本列島で稲作を主とする食料生産に基礎を置く生活が始まった最初の文化。鉄器、青銅器が出現して石器が消滅し、紡織が始まり、階級の成立、国家の誕生に向かって社会が胎動し始めた」(小学館『世界大百科事典』)——の範囲で使われるようになったのが、壺、甕、鉢、高杯などを主な器種とする弥生土器だ。実は、縄文土器と弥生土器の間に技術的な革新はない。変化したのは、造形意識だけだ。縄文土器が口縁部を中心に、呪術的、神話的な装飾を施しているのに対して、弥生土器は磨いた肌や輪郭の曲線の美しさ、先の尖った工具で器体に施した線文(回転台を用いる作も)などを特徴とする。
 壺型土器 弥生時代・前2~前1世紀、茨城県筑西市 女方遺跡出土、東京国立博物館蔵(田中国男氏寄贈)
壺型土器 弥生時代・前2~前1世紀、茨城県筑西市 女方遺跡出土、東京国立博物館蔵(田中国男氏寄贈)
やきものに技術的なイノベーションが起こるのは、その後だ。やきものは大まかに、土器(縄文土器、弥生土器、土師器など)、炻器(須恵器、常滑焼、備前焼、信楽焼など)、陶器(緑釉陶器、奈良三彩、古瀬戸、美濃焼、唐津焼、萩焼、京焼、益子焼など)、磁器(伊万里焼、鍋島焼、江戸時代後期の九谷焼、京焼、瀬戸焼、美濃焼など)の4種類に分けられる。ここまで紹介してきた土器は、山野から採集してきた粘土をそのまま使い、焚き火のような形式の野焼きで、低い温度(700〜900度)で焼成されるタイプ。焼き締まっていないため、吸水性が高く、壊れやすい。
ところが古墳時代になると、朝鮮半島から渡来した工人たちによって、まったく新しいやきものが作られるようになる。それが須恵器だ。粘土を一定の太さの紐状にして器の形に積み上げ、叩き台と当て具を使って内外から叩き締めると、素地は薄くなり、粘土中の空気も減って強度が増す。さらに窖窯を使って高温で焼くことで、土器よりずっと薄くてシャープな形で、堅く吸水性も少ない(時に陶器に分類されることもある)やきものができる、というわけだ。
大陸のテクノロジーを採り入れた須恵器が登場しても、やきものはまだ、いまひとつ地味な感じが否めない。なぜなら、ほとんど粘土そのままの色、あるいは焼成によってやや灰~青~黒っぽい色を呈するか、いずれにしてもまさに「地」味、ナチュラル・ボーン・ネンド、だからだ。中にはベンガラを用いて赤色の装飾を施した例もあるが、そう多くはない。
 須恵器子持高坏 古墳時代・6世紀、高27╳幅36.5cm、岡山市 冠山古墳出土、東京国立博物館蔵
須恵器子持高坏 古墳時代・6世紀、高27╳幅36.5cm、岡山市 冠山古墳出土、東京国立博物館蔵
そこに多彩な色が現れるのは、奈良時代に入ってから。飛鳥時代には比較的低い温度で溶ける釉薬、中でも「なまりぐすり」と呼ばれた鉛釉を使って、緑色の陶器を焼く技術が、朝鮮半島から伝えられていた。それまでの、土の塊のようなやきものとは違う、翡翠のような色、艶で飾られたやきものは、当時の貴族や寺院での儀式、宴席で用いる高級品として珍重された。やがて奈良時代になると、中国・唐で大流行した「唐三彩」に影響を受け、黄褐色や白の釉薬を加えた「奈良三彩」が登場。朝鮮半島や中国から直接輸入したものだけでなく、国内でも多彩なやきものを焼く技術が育っていった。
 奈良三彩壺 奈良時代・8世紀、高13.7╳胴径21.3╳高台径13.5cm、伝滋賀県出土、九州国立博物館、重文
奈良三彩壺 奈良時代・8世紀、高13.7╳胴径21.3╳高台径13.5cm、伝滋賀県出土、九州国立博物館、重文
 緑釉四足壺 平安時代・9世紀、高18.8╳口径8.8╳胴径22.9cm、猿投窯、九州国立博物館、重文
緑釉四足壺 平安時代・9世紀、高18.8╳口径8.8╳胴径22.9cm、猿投窯、九州国立博物館、重文

橋本麻里(はしもと・まり)
日本美術を主な領域とするライター、エディター。公益財団法人永青文庫副館長。金沢工業大学客員教授。著書に『美術でたどる日本の歴史』全3巻(汐文社)、『京都で日本美術をみる[京都国立博物館]』(集英社クリエイティブ)、『変り兜 戦国のCOOL DESIGN』(新潮社)、共著に『SHUNGART』『原寸美術館 HOKUSAI100!』(共に小学館)、編著に『日本美術全集』第20巻(小学館)。ほか多数。