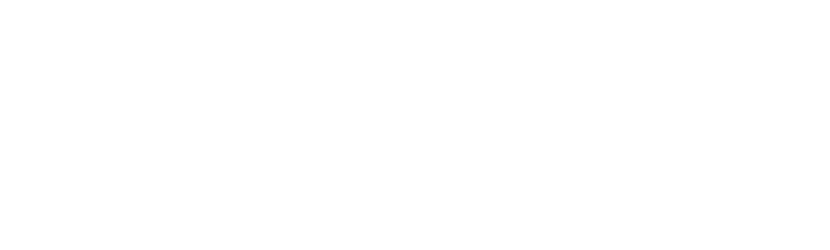【やきもんロワイヤル副読編 ~やきものこぼれ話~】 第4回「日本のやきもの、ついに世界デビューを果たす」
20/08/21
月刊「モーニング・ツー」
(毎月22日頃発売)にて、竹谷州史氏が描くやきもの擬人化コメディ『やきもんロワイヤル』。
この作品の監修を務める日本美術ライターの橋本麻里さんに、やきもの知識満載のコラムをお願いしました。
毎月これを読めば『やきもんロワイヤル』がさらに楽しめるようになること請け合い!
(第1回 /第2回 /第3回 )
江戸時代前期の焼物の特徴は、豊臣秀吉が朝鮮半島に出兵した「文禄・慶長の役」(1592~98)において、西国大名たちが日本へ連れ帰った朝鮮人陶工たちの技術から生まれた。毛利家萩藩の御用窯(藩が直接運営した窯)である萩焼、島津家薩摩藩の薩摩焼、黒田家福岡藩の高取焼などに代表される窯は、いずれも朝鮮人陶工によって開かれたものである。
御用窯としての萩焼は、茶碗、茶入、花入などの茶陶を中心に、一般庶民向けの日用雑器なども大量に焼いた。茶人の間では「一楽、二萩、三唐津」と言われて高い評価を得、また朝鮮半島で焼かれた、いわゆる高麗茶碗を写したものも、数多くつくられている。1200度ほどの比較的低い温度で焼成するため、焼き締まりが甘くなるが、これを使っているうちに茶が染みて、釉の色合いや調子が変化することから、「萩の七化け」の俗称がある。
中世まで全く焼物作りとは無縁の地だった薩摩では、御用窯だけでなく、朝鮮人陶工が民間の窯も開き、それぞれ活発に活動した。この薩摩焼には、「黒もん(黒薩摩)」と「白もん(白薩摩)」の2種がある。
 黒釉文琳茶入 銘 望月 17世紀、高7.6╳口径2.8╳底径2.8cm、松永安左エ門氏寄贈、東京国立博物館蔵
黒釉文琳茶入 銘 望月 17世紀、高7.6╳口径2.8╳底径2.8cm、松永安左エ門氏寄贈、東京国立博物館蔵
 白釉蓮葉茶碗 17世紀後半、高8.9╳口径14.4~11.5╳底径5.8cm、東京国立博物館蔵
白釉蓮葉茶碗 17世紀後半、高8.9╳口径14.4~11.5╳底径5.8cm、東京国立博物館蔵
「黒もん」は鉄分の多い土に黒釉をかけたもので、日用雑器だけでなく、高級な茶陶もつくられた。一方「白もん」は、白土に透明釉をかけた陶器。中でも「火計り手」と呼ばれる白無地の茶碗は、朝鮮の土と釉を使い、火(焼成)は日本で行う(=火以外の材料や技術がすべて朝鮮のものである)ことから数が少なく、大切にされてきた。
これらの窯に続き、朝鮮人陶工が持つ技術によって、日本では1610年代、佐賀県有田地方で初めて焼かれるようになったのが、「磁器」だ。鉄分の少ないカオリン土を素焼きにして釉薬をかけ、陶器より高温の1100~1500度で焼く。すると、吸水性がほとんどなく、叩くと金属的な音を発する硬質のやきものができる。6世紀の中国(北斉)で完成されたこの「磁器」は、桃山時代には中国から大量に輸入され、日本でも大変な人気を博していた。国内での製造を目指すのは、当然のことだろう。
つくり手の中心となったのは朝鮮人陶工だが、彼らが手本としたのは、当時世界的に需要の高かった中国・景徳鎮窯の「染付」だ。
 青花束蓮文皿 明時代(15世紀)、比佐隆三氏寄贈、東京国立博物館蔵
青花束蓮文皿 明時代(15世紀)、比佐隆三氏寄贈、東京国立博物館蔵
 青花吹墨玉兎文皿 明時代末期(17世紀)、高3.9╳口径28.5╳高台径18.8cm、九州国立博物館蔵
青花吹墨玉兎文皿 明時代末期(17世紀)、高3.9╳口径28.5╳高台径18.8cm、九州国立博物館蔵
少し寄り道をして、染付の話をしよう。白いキャンバスのような地に、青色の顔料を使い、筆で文様や絵柄を描いた「染付」は、世界中のもっとも多くの地域で作られている、加彩の焼物かもしれない。白と青に彩られた器は、涼やかな清潔感を持ち、どんな料理の邪魔もしないからだ。中国語で「青花」、日本語なら「染付」、英語では「Blue & White」と呼ばれた白地に青の陶磁器が最初に生まれたのは、9~10世紀頃のメソポタミア地方、またはペルシア地方とされる。この地域では残念ながら磁器(素地のガラス質が磁化して半透明となり、吸水性がほとんどない、叩くと金属質の清音を発する硬い焼物)の原料となる土が採れなかった。一方、唐時代末期から陶磁器の生産が本格化した中国では、国外への輸出にも力を注いだため、この時代の青磁は、エジプト・カイロ近郊の遺跡でも見つかっている。
やがて大陸の東西で交易が活発になると、ペルシアで産出する良質の青色顔料「回青」(酸化コバルト、回教の地に産することから回青と呼ばれた)が中国へ運ばれ、白と青に彩られた磁器が生まれる。9世紀の遺跡から発掘された陶片からは、輸出先であるアッバース朝のムスリムたちが好むであろう、イスラム陶器を模した柄の磁器が出土しており、既に周到なマーケティングが行われていたことを伺わせる。
こうして生まれた染付が爆発的に世界中へ広がっていくのは、宋を滅ぼして勃興した元(1271~1368年)の時代だ。宋時代まで輸出用の主力商品は青磁だったが、この頃には新しいものが望まれていた。そこへ登場したのが、景徳鎮で大量生産され始めた染付なのだ。
 青花龍濤文壺 元時代(14世紀)、東京国立博物館蔵
青花龍濤文壺 元時代(14世紀)、東京国立博物館蔵
西はヨーロッパ東部からトルコ、チベット、朝鮮半島まで、人類史上最大の版図を実現した元は、内陸を貫通するシルクロード、南シナ海からインド洋へ至る「海の道」を結び合わせた。「ここにユーラシア世界は、東は日本列島から西はブリテン島まで、広く連鎖の輪の中につながれた」(杉山正明『モンゴル帝国の興亡』下巻、講談社現代新書)のである。当初は民間交易だったが、商機ありと見た政府が官営事業として参入、交易は拡大していった。
染付は地中海交易を通じて、ヨーロッパにもある程度輸入されていた。その量が一気に増え、王侯貴族たちのコレクションになっていくのは、17世紀初頭頃からだ。15世紀の末に大航海時代が幕を開けると、ポルトガル、スペイン、オランダらが国の威信を賭けて海上貿易を展開。中でもオランダは積極的に極東へ進出してオランダ東インド会社を設立、拿捕したポルトガルの交易船の積荷にあった染付をオークションにかけたことをきっかけに、陶磁器交易の主導権は、それまでのアラビア商人からオランダへ移っていく。
染付に限らず、絹織物や漆器、香料、茶葉など、中国からもたらされる珍奇で美しい品々は、たちまちヨーロッパの人々を魅了し、空前のシノワズリ(中国趣味)が席巻した。一方、イスラム圏からイベリア半島経由でヨーロッパへ伝わり、マヨルカ島で発展した技術を受け継いだオランダのデルフトでは、陶土に白い錫釉をかけ、酸化コバルトで青花風の図柄を写したもの、やがてその図柄にオランダの風物や聖書の場面などを採り入れた陶器が焼かれた。これが高級陶器として多くの顧客を獲得すると、さらにその写しがイギリスなどで作られるようになる。
 染付花鳥文瓢形瓶 17世紀、高38.1╳口径7.9╳底径13.8cm、東京国立博物館蔵
染付花鳥文瓢形瓶 17世紀、高38.1╳口径7.9╳底径13.8cm、東京国立博物館蔵
元の滅亡後、明で染付の大量生産は続いたが、17世紀後半の明の衰退に伴う混乱の中で、約30年ほど景徳鎮の生産が止まってしまった時期がある。ヨーロッパにはまだ磁器を焼成する技術もなく、そこでオランダ東インド会社が目をつけたのは、朝鮮人陶工の技術で磁器製造に成功した日本の九州・有田の窯だった。
 染付吹墨月兎図皿 江戸時代(17世紀前半)、高2.4╳口径19.9╳底径8.5cm、東京国立博物館蔵
染付吹墨月兎図皿 江戸時代(17世紀前半)、高2.4╳口径19.9╳底径8.5cm、東京国立博物館蔵
 染付雲龍文鉢 江戸時代(17世紀)、高10.0╳口径29.7╳底径17.9cm、東京国立博物館蔵
染付雲龍文鉢 江戸時代(17世紀)、高10.0╳口径29.7╳底径17.9cm、東京国立博物館蔵
ここで焼かせた中国風の染付や柿右衛門様式の色絵磁器も大ヒット商品となり、積み出し港である「伊万里」の名で、ヨーロッパに広まるのである。
 色絵獅子牡丹文壺 江戸時代(17世紀)、高21.7╳口径10.2╳底径10.2cm、東京国立博物館蔵
色絵獅子牡丹文壺 江戸時代(17世紀)、高21.7╳口径10.2╳底径10.2cm、東京国立博物館蔵
 色絵花卉文大壺 江戸時代(17世紀)、高35.0╳口径14.4╳底径15.7cm、東京国立博物館蔵
色絵花卉文大壺 江戸時代(17世紀)、高35.0╳口径14.4╳底径15.7cm、東京国立博物館蔵

橋本麻里(はしもと・まり)
日本美術を主な領域とするライター、エディター。公益財団法人永青文庫副館長。金沢工業大学客員教授。著書に『美術でたどる日本の歴史』全3巻(汐文社)、『京都で日本美術をみる[京都国立博物館]』(集英社クリエイティブ)、『変り兜 戦国のCOOL DESIGN』(新潮社)、共著に『SHUNGART』『原寸美術館 HOKUSAI100!』(共に小学館)、編著に『日本美術全集』第20巻(小学館)。ほか多数。