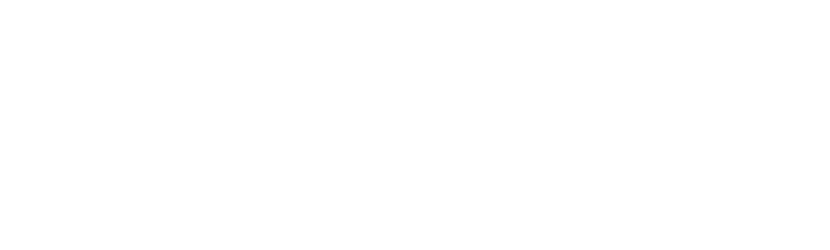【やきもんロワイヤル副読編 ~やきものこぼれ話~】 第5回「やきものの成熟、そして現代へ」
20/10/22
月刊「モーニング・ツー」
(毎月22日頃発売)にて、竹谷州史氏が描くやきもの擬人化コメディ『やきもんロワイヤル』。
この作品の監修を務める日本美術ライターの橋本麻里さんに、やきもの知識満載のコラムをお願いしました。
毎月これを読めば『やきもんロワイヤル』がさらに楽しめるようになること請け合い!
ついに最終回です!
(第1回 /第2回 /第3回 /第4回 )
文禄・慶長の役(1592~93、1597~98)の折に朝鮮半島から連れ帰られた陶工たちによって、西日本各地で新しい窯(萩焼、薩摩焼、高取焼など)が起こる一方、有田では磁器の生産に成功。明末の政治的混乱に巻き込まれた景徳鎮の停滞に乗じてヨーロッパへの輸出商品へ成長していくなど、江戸時代前期は焼物の世界でも大きな変動が起こっていた。一方、文化の中心たる京都も、ただ焼物先進地の後塵を拝していたわけではない。
一般的に「○○焼」「○○窯」と呼ばれるような焼物の発祥は、まず焼物に向いた土が見つかり、周辺地域の日常生活用の器を賄うところから産業として成長を始める。ところが「京焼」と総称される京都を基盤とした焼物は、当初から嗜好品、高級品として作られ始めた、特異な、そして非常に都市的な焼物であった。
17世紀半ば、有田で染付に続いて色絵磁器が誕生した頃、京都でも華やかな色絵の焼物が作られ始めた。ただしこちらは磁器ではなく陶器の色絵。しかも伊万里焼のように、中国の磁器を写すところから始まったわけではないため、色絵といってもずいぶん雰囲気が違う。これを大成したのが、野々村仁清だ。
 野々村仁清《色絵月梅図茶壺》 17世紀、高29.9╳口径10.6╳底径11.4cm、東京国立博物館蔵、重文
野々村仁清《色絵月梅図茶壺》 17世紀、高29.9╳口径10.6╳底径11.4cm、東京国立博物館蔵、重文
 《銹絵山水水指》 17世紀、通蓋高20.0╳口径13.8╳底径8.6cm、東京国立博物館蔵
《銹絵山水水指》 17世紀、通蓋高20.0╳口径13.8╳底径8.6cm、東京国立博物館蔵
丹波国「野々村」(現京都府美山町)の出身で、本名「清右衛門」。ゆえにその門前に窯を築いた「仁」和寺と「清」右衛門から一字ずつを採って、野々村仁清を名乗った。そして樂茶碗を焼いた長次郎が千利休のディレクション下にあったように、仁清にも当初からプロデューサーがいた。それが茶人の金森宗和である。
かつて豊臣秀吉と千利休のつながりの中で一度標準化された後、再び多様化に向かっていた茶の湯の世界にあって、古田織部や小堀遠州、片桐石州が武家の茶なら、宮廷や公家には、また異なる茶の湯の文化が育っていた。その中で指導的役割を果たしたのが、戦国武将の嫡男でありながら廃嫡となり、京都に隠棲、優美な茶風から「姫宗和」と呼ばれた金森宗和だった。仁清は土地の土や伝来の技法を活かすのとはまったく別に、茶人宗和の美意識を体現する陶工として登場したのだ。

 《色絵波に三日月文茶碗》 17世紀、高9.1╳口径12.6╳底径4.8cm、東京国立博物館蔵※箱書に「宗和老ヨリ来仁和寺焼 茶埦 俊了」とあり、この茶碗が金森宗和の指導の下で焼かれていた頃の作とわかる。
《色絵波に三日月文茶碗》 17世紀、高9.1╳口径12.6╳底径4.8cm、東京国立博物館蔵※箱書に「宗和老ヨリ来仁和寺焼 茶埦 俊了」とあり、この茶碗が金森宗和の指導の下で焼かれていた頃の作とわかる。
磁器と違い、素地そのままでは色を引き立たせる白いキャンバスとなり得ない陶器の場合、まず水で溶いた白色の化粧土を掛け(白化粧)、その上に色絵や金銀彩を施していく。磁器のような透明感のある白色とは異なる、柔らかな象牙色の釉肌に、絵画や染織の優美なモチーフを自由に採り入れて絵付けする仁清の斬新なスタイルは、大名を中心とする武家茶の茶道具として大きな人気を博すようになっていった。
続く京焼の旗手が、琳派のスターとして名高い尾形光琳の弟、乾山(号は深省)である。兄弟は後水尾天皇の后、東福門院を上顧客とする超高級呉服商、雁金屋に生まれ、遡れば曾祖母は本阿弥光悦の姉。兄弟は光悦の蒔絵や俵屋宗達の屏風が身近に存在する世界で育った。当主である父が亡くなったのは、乾山25歳の時。兄弟は家屋敷の他、莫大な大名貸しの証文を相続するが、兄・光琳の底が抜けた遊蕩、さらに大名家による借金の踏み倒しに遭い、雁金屋は破産。自活せざるを得なくなった兄弟は、身についたセンス、蓄積した技術や教養を武器に、光琳が絵画、乾山が陶芸の道を進むことになる。
乾山は2代仁清に師事して焼物を学ぶと、元禄12年(1699)、近くの鳴滝泉谷に窯を築いて独立した。この窯が都の乾(西北)の方角にあたるため、「乾山」を窯の名に、さらに製品の商標、また彼自身の雅号にも用いるようになったといわれる。
乾山は兄の光琳が得意とした華麗な琳派風の意匠、漢詩を元にした水墨画風の銹絵、和歌に基づくやまと絵風の色絵と、それまでにない文学性・絵画性を京焼の中に持ち込む一方、東南アジアやヨーロッパの陶磁の写しも積極的に行った。兄・光琳が絵を描き、乾山が賛(絵に関連した詩文)を記した兄弟合作の皿などからも明らかなように、乾山は陶器本体があたかも料紙であるかのように絵や文字を描き、その縁を切り取ったり、透かし模様を入れたりしている。
 尾形乾山《色絵椿図香合》 18世紀、総高2.6╳径7.5╳底径7.7cm、東京国立博物館蔵
尾形乾山《色絵椿図香合》 18世紀、総高2.6╳径7.5╳底径7.7cm、東京国立博物館蔵

 尾形乾山《銹絵十体和歌短冊皿》10客 寛保3年(1743)、各縦28.7cm、東京国立博物館蔵
尾形乾山《銹絵十体和歌短冊皿》10客 寛保3年(1743)、各縦28.7cm、東京国立博物館蔵

 尾形光琳・深省《銹絵観鷗図角皿》 18世紀、高2.9╳径22.2cm、東京国立博物館蔵
尾形光琳・深省《銹絵観鷗図角皿》 18世紀、高2.9╳径22.2cm、東京国立博物館蔵
現代に生きる私たちは、平面は平面、立体は立体、あるいは画家は画家、陶芸家は陶芸家と、まったく独立したジャンルとして考えるのが習い性になっている。だが平面と立体の間を自由に往還した琳派の絵師たちにとって、絵絹に描いた花の姿を、蒔絵の文箱に配せるようにデザインしなおすのは、至極当然の話であった。彼らは生活のさまざまな場面を、趣味よく、そして贅沢に彩ることをこそ、本懐とするからだ。そもそも琳派の祖にして、刀剣の鑑定や研ぎを家職とする本阿弥家出身の光悦からして、自身が屈指の能筆、茶陶の名手として知られる一方、鉄の刀身から刀装を彩る染織、皮革、牙彫、漆工など多彩な工芸技術に通じ、オーケストラのように複数の領域の職人を指揮して、作品を作りあげていたのだから。その系譜に連なる乾山もまた、絵や書のように「観る」ことを重視した、新しい器のあり方を探求していたのだ。
 尾形光琳《八橋蒔絵螺鈿硯箱》 18世紀、東京国立博物館蔵、国宝
尾形光琳《八橋蒔絵螺鈿硯箱》 18世紀、東京国立博物館蔵、国宝
 尾形光琳《小袖 白綾地秋草模様》 18世紀、身丈147.2╳裄65.1cm、東京国立博物館蔵、重文
尾形光琳《小袖 白綾地秋草模様》 18世紀、身丈147.2╳裄65.1cm、東京国立博物館蔵、重文
こうした色絵陶器は17世紀後半以降さらに普及し、粟田口の窯を中心に、茶陶はもちろん、花入、手焙り、香炉などの調度類、皿、向付、重箱などの食器類が多数焼かれた。これらを「古清水」と呼び、江戸時代後期に清水五条坂で量産されるようになった磁器と区別している。
 《色絵椿松竹梅文透入重蓋物》 18世紀、総高25.6╳口径19.6╳底径19.5cm、東京国立博物館蔵
《色絵椿松竹梅文透入重蓋物》 18世紀、総高25.6╳口径19.6╳底径19.5cm、東京国立博物館蔵
ここから再び、九州の磁器に視線を戻そう。17世紀初頭、磁器の焼成に成功した有田では、純白に近い素地——初めての「白いカンヴァス」を獲得した。まず染付が先行し、1640年代には色絵具を焼きつける技法が完成。この初期色絵様式を、俗に「古九谷」と呼ぶ。かつては九谷(現石川県加賀市)で焼かれたと考えられていたからこその名称だが、「古九谷」の意匠の重厚さや格調の高さは、後述する鍋島様式や柿右衛門様式と比べても、ひとまわりスケールが大きい。この国産色絵磁器がどこで最初に生まれたか、学界でも長い間、有田説と九谷説が拮抗していた。だが考古学的な調査の蓄積により、1640~50年代に有田で焼かれた色絵磁器とすることでほぼ決着している。
 《色絵草花文輪花平鉢》 17世紀、高6.7╳口径34.7╳高台径18.4cm、東京国立博物館蔵
《色絵草花文輪花平鉢》 17世紀、高6.7╳口径34.7╳高台径18.4cm、東京国立博物館蔵
この有田を擁する肥前佐賀を治めていたのは、鍋島家である。17世紀前半から佐賀藩が経営する藩窯で焼かれた最高級磁器を、鍋島焼と呼び、伊万里焼の一様式ととらえることもある。鍋島焼は一般に販売、輸出されることはなく、将軍家への献上、または幕閣の要人や他の大名家への贈答に用いるのみ。皿がほとんどで、文様の斬新さ、精緻さを身上とする。そのため技術・情報の流出を許さず、大川内の山中(※)に窯場を築いて職人を住まわせ、藩の関係者以外の出入りを禁じるなど、まさに「門外不出」を貫いた御用窯であった。
※伊万里市街から車で10分ほど、現在は「秘窯の里 大川内山」として、古窯跡や墓域、神社など、歴史的文化財や景観を保存、公開している。
 《色絵唐花文皿》 17~18世紀、高5.4╳口径20.1╳底径10.8cm、東京国立博物館蔵
《色絵唐花文皿》 17~18世紀、高5.4╳口径20.1╳底径10.8cm、東京国立博物館蔵
こうしてヨーロッパを席巻した伊万里焼だったが、中国国内が安定を取り戻すと共に磁器の世界市場へ復帰。18世紀の中頃には伊万里焼は価格競争に破れ、海外輸出は途絶えた。それでも伊万里焼は国内市場、中でも庶民の用いる食膳具として、隅々まで磁器を普及させる方向へ舵を切り、磁器の国内流通量を大幅に増大させていく。その結果、各藩がそれぞれ自前で磁器生産の模索を始め、19世紀初頭にはいち早く瀬戸・美濃で磁器の製造が始まった。やがて明治を迎えるとヨーロッパから新たな技術がもたらされ、日本各地の窯場は、再編の嵐に巻き込まれていくのである。
ご愛読ありがとうございました。引き続き、『やきもんロワイヤル』本編をお楽しみくださいませ!

橋本麻里(はしもと・まり)
日本美術を主な領域とするライター、エディター。公益財団法人永青文庫副館長。金沢工業大学客員教授。著書に『美術でたどる日本の歴史』全3巻(汐文社)、『京都で日本美術をみる[京都国立博物館]』(集英社クリエイティブ)、『変り兜 戦国のCOOL DESIGN』(新潮社)、共著に『SHUNGART』『原寸美術館 HOKUSAI100!』(共に小学館)、編著に『日本美術全集』第20巻(小学館)。ほか多数。